株式会社ジェネレーションパスは、今や年商100億円を超えるECサイト「リコメン堂」を運営する企業。
しかし、以前はEC売上の急拡大に伴い、システムやオペレーションに課題が生じていました。
その課題を解決したのが、自社開発の受発注システム「GPMS」です。
そこで今回は、年商20億から100億までの過程や当時の状況、課題やその後の成果などについて、システム開発担当者であり、現在取締役を務める桐原幸彦さんにインタビューを行いました。
編集の都合上、インタビュー内容を一部簡略化・言い換えしております。予めご了承ください。
この記事を書いた人:受発注ライフ編集部
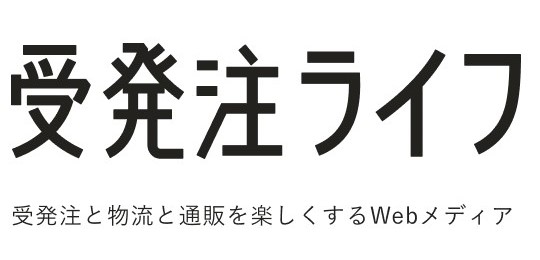
『受発注ライフ』は、2024年3月22日に誕生した、株式会社カンナートのWebメディアです。
株式会社カンナートは西新宿にある創業20年目のシステム開発会社です。
このメディアでは、受発注業務や物流、通販にお困りごとのある方々に向けて、 業務改善のアイデアや業界の新しい動向などを発信していきます。
ー「リコメン堂」が好調のようですが、年商20億円規模の当時の状況について教えていただけますか。

ECをはじめて、マーケティングがうまくいった結果、どんどん売上が伸びてきて年商20億円程度まで大きくなっていました。
ただ、売上の増加にともなって、オペレーションの量も比例して増加していったため、社員数、社員の残業時間も右肩あがりでした。
当時は既存の受注管理ツールを使用していたのですが、注文量の増加とともに動作が重くなって、状況によってはシステムの起動に30分かかることもありました。
そのため、社員が自宅からリモートアクセスでシステムを起動して、それから出社する、といったルーティンをしている時期もありました。
また、同時に使えるユーザー数にも制限があり、人海戦術をするにも限界を迎えていました。
そのような状況の中で、当時の私は会社全体のシステム部門の責任者として、上記のような問題を抱えた状況を、早急に改善しなければならない立場におりました。
ー 当時の課題にはどのようなものがありましたか。
当時の課題は、システムの動作が重くなっていたことと、ECのオペレーションが複雑になっていたことの大きく2点がありました。
当時使用していたシステムの想定注文数をはるかに超える量をさばいていたので、仕方なかったのですが、最初はデータを整理したり、オペレーションを変更したり、既存のツールをたたくバッチシステムを導入したりしていました。
また、取り扱い商品ジャンル、店舗数、提携倉庫数、取引先数、決済種別も増加し、オペレーション上の分岐点となる項目が増えることで、加速度的にオペレーションのパターンが増加していきました。
それに伴い、属人化した業務フローが増えてきており、担当者の不在・異動・退職時によって、業務が滞ってしまうリスクも増大していました。
ー その課題に対してどのような対応を取りましたか。
最初の3ヶ月は、全ての部署に対してヒヤリングを行いながら、データの整理やバッチシステムの導入など工夫しながら対応してきましたが、根本的な解決にはならなかったので、システムのリプレースを決意しました。
当時の中期計画では年商100億円を掲げていたので、20億円から100億円に増加することを意識し、売上と注文数の増加に合わせて、チューニング可能な自社システムの設計を行いました。
自社開発した受発注システム「GPMS」により、複雑化していた多くのオペレーションをシステム上で処理できるようになりました。
例えば、複数商品を含む注文では、商品ごとに発注先や在庫状況(自社倉庫に在庫があるのか、メーカー在庫なのか)が異なる場合があります。
弊社は取引先が数百社にのぼるため、複数商品を含む注文であっても、条件に応じて自動発注する仕組みを開発し、出荷までのリードタイムを短縮しました。
また、商品の在庫数は常に変動するため、欠品してしまうと機会損失になってしまいます。
そこで、商品ごとに発注タイミングを柔軟にコントロールするため、こちらも条件に応じて自動で発注するシステムを組み込みました。
さらに、決済方法によっては与信の通過タイミングが異なるため、それを検知してから発注を行う処理もシステム化に成功しました。
新たに店舗やジャンル、倉庫、取引先、決済種別が追加された場合でも、業務フローを再策定し、システムに設定するだけで対応できるようになったのも、自社開発ならではだと思います。
結果として、大きなオペレーション変更をせずに柔軟な運用が可能になりました。
ー 対策を実施する際に困ったことはありましたか。
目の前で社員が困っている中で、開発しなければならない状況だったので、短期間で効果が出る機能に絞り、早期にリリースしなければと焦っていました。
しかし、現場の社員からは、「小手先の改善ではなくて、ちゃんと直してください。それまでは頑張りますので。」と言われて、さらにプレッシャーを感じました。
また、EC店舗を運営している中で、システム開発してリリースするため、リリースに失敗した場合に大きなリスクがあると感じていました。
ー 開発担当者としては確かにプレッシャーに感じますね。どうやってそのプレッシャーを乗り越えましたか。
社長自ら現場の社員に、「必ず今回のシステム開発で早く動くようになるから、それまでシステムに協力してくれ。」って何度も声をかけてくれました。
社長の号令と現場の社員のシステム改善への強い意欲もあり、本当に協力してくれました。
自社システムを構築するときは、開発サイドとユーザーサイドが一体となって取り組むことが重要だと感じた瞬間でした。

ー 会社で一体となって自社開発に取り組めたのですね。改善策実施後、どのような変化がありましたか。
システム導入前の2012年は売上が約28億円、取引先数が188社でしたが、1年後の2013年には売上が約35億円まで増加し、取引先数も250社へと拡大しました。
かつては、システムの起動に30分もかかっていたため、社員は出社前に自宅からリモートでシステムを立ち上げるという、今思えば信じられないような習慣を続けていました。
それが、システムの刷新によりスムーズに起動するようになり、私たちはようやく“普通”の状態を取り戻すことができました。
オペレーションもゼロベースで見直し、再構築しました。
すると、自然と「自動化できるものは自動化しよう」という意識が現場に広がっていきました。
そんなある日、ひとりの社員がふと漏らした言葉が忘れられません。
「太陽が出ているうちに会社を出たの、何年ぶりだろう。」
その何気ない一言に、これまでの苦労や我慢、そしてこの改革の意味がすべて凝縮されているように感じました。
実際、導入前は社員7名で回していたオペレーション業務も、現在はアルバイト5名が日々の業務を担い、社員2名でイレギュラー対応や業務フロー改善を行うように体制が変わりました。
もともとみんなマーケティングがやりたくて入社したはずなのに、気がつけばオペレーションのスペシャリストになってしまっていた――。
それが、システムに任せられるようになったことで、本来やりたかったマーケティングの部署へ次々に異動していったのです。
さらに、新しいオペレーションを柔軟にシステムへ組み込めるようになったことで、現場からも「こうしたらもっと良くなる」という改善提案が次々とあがるようになりました。
この自社開発は、システムが改善しただけではなく、「人の力を活かす場所」を変えてくれたのだと思います。
その後、システムも組織も改善され業績も順調に成長したことで、結果的に弊社は無事に上場することができました。

ー 現場の苦労を知っているからこそ、システム改善の意義をより感じたのではないかと思います。当時の桐原さんと同じように困ってる人や企業に何かアドバイスはありますか。
ECの売上は、全ての部署が関わって売上を上げていると私は考えています。
カスタマーサポート、オペレーション、マーケティング、ページ制作、商品の選定仕入れなど、すべての部署の仕事が少しずつ貢献して売上を作っています。
ECのシステムは、そのすべての部署の人に関係する重要なパーツです。
弊社では、社長をはじめとした経営陣の理解もあり、すべての部署がECシステムのリプレースに協力してくれました。
システム開発部だけでなく、全員で協力して取り組んだことが成功した大きな理由だと思います。
また、私にとっては、企業の基幹システムをリプレースすることは大きな挑戦でした。
システムは「動いて当たり前」なので、もちろん失敗してはいけないのですが、挑戦しなければ失敗しませんし、挑戦しなければイノベーションは生まれません。
失敗を恐れずに「挑戦」を選んだ結果が売上増に繋がったのだということを、当時の私と同じような立場で、同じ悩みや課題を抱えられている企業の方には、ぜひともお伝えしたいです。
ー まとめ
受発注の現場担当者さんにお話を聞くこの企画。
今回は、株式会社ジェネレーションパスのシステム開発に携わった桐原幸彦さんにお話を聞きました。
当時のリアルなエピソードに思わず胸を打たれますね。
今後は社内だけに留めず、さまざまな裏話を公開していきますので、ぜひ楽しみにしていてください!

