1人または複数人が、作業にミスがないか確認するダブルチェック。
ダブルチェックにはクロスチェックなど色々な方法があり、業務内容や掛けられるコストによって適したやり方が異なります。
記事では、ダブルチェックのやり方の種類から言い換えの言葉や目的を紹介。
さらに、ダブルチェックは意味がないと言われる理由、形骸化する要因についても解説します。
ミスを減らすチェックのコツを知りたい人はぜひ読んでみてください。
この記事を書いた人:受発注ライフ編集部
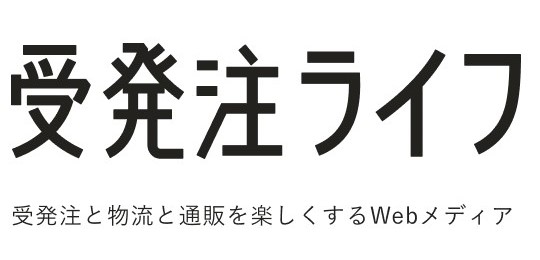
『受発注ライフ』は、2024年3月22日に誕生した、株式会社カンナートのWebメディアです。
株式会社カンナートは西新宿にある創業20年目のシステム開発会社です。
このメディアでは、受発注業務や物流、通販にお困りごとのある方々に向けて、 業務改善のアイデアや業界の新しい動向などを発信していきます。
ダブルチェックとは?

最初にダブルチェックの意味・目的を確認し、ダブルチェックとは何か理解を深めましょう。
言い換えについても解説します。
ダブルチェックの意味や目的とは?
仕事をする中でミスがないか複数回にわたって確認するダブルチェック。
1回目の確認で見逃していたミスを2回目の確認で発見し、取り除く目的があります。
医療現場や金銭の授受、工場内だけでなく、オフィスでの資料作りなどにも有効です。
ダブルチェックの言い換えは?
ダブルチェックの言い換えはあるのでしょうか。
言い換えとしては、「再点検」や「再確認」といった言葉が挙げられます。
ダブルチェックの方法とやり方

「ダブルチェック」と一口にいっても、実はさまざまな方法があります。
見落としを防ぐそれぞれのダブルチェックのやり方を確認していきましょう。
1人連続型
1人の同じ人物が、続けて2回検証する手法のことです。
2人で確認するやり方よりも信用度には欠けますが、人手不足や時間がないとき、またはコストをかけられないときに用いられます。
ミスが比較的起こりづらい、簡単な確認でよく使われる手段です。
1人時間差型
こちらも1人連続型と同じように1人でチェックするやり方ですが、違うのは1回目と2回目の確認作業の間隔を空ける点。
時間を空けて気持ちを切り替えてチェック作業を行うと、最初の確認で見逃していたエラーに気が付きやすくなります。
コストや人数の問題で、2人でチェックができない場合に有効な方法です。
1人双方向型
同じ人物が作業に誤りがないか2回確かめる方法ですが、2回目は1回目と異なる方向から検証します。
異なる視点から確認することで見え方が変わり、間違いや見落としを見つけやすくなるのが特徴。
1人時間差型と同じくらいの効果が期待できるといえます。
2人連続型
2人連続型は、2人が連続して同じ手順でチェックするやり方のことで、職場でよく用いられるダブルチェック方法です。
検証する人物を変えるとミスに気づきやすいとされるため、同じ担当者が2度確かめるよりも有用です。
2人連続双方向型
最初の担当者が確認した方向とは別の方向から次の人物が確認していきます。
例えば、1人目が文章を上から読んで間違いがないか確認した場合、次の人は文書の最後から文をチェックしていきます。
違う視点から確認するため、2人連続型よりもミスや見落としが見つかりやすくなるでしょう。
トリプルチェック
文書や作業に誤りがないか3名が確かめる方法です。
異なるメンバーが3回チェックするため、ミスを見つけやすくなります。
しかし、「他の人がチェックしたから大丈夫」と考えて無意識に気が緩んで、見落としが発生することもあるので注意しましょう。
クロスチェック
クロスチェックとは、1回目と違うやり方や観点で何度か確認検証する手法のこと。
例えば、薬局では薬剤師が医師が作った処方箋を確認します。
医師とは異なる薬剤師の観点から、薬が適切か確認することで処方ミスを防ぐのが目的です。
クロスチェックは他の方法よりも工数やコストがかかりますが、正確性は向上します。
ダブルチェックは形骸化して意味ない?

ダブルチェックをしてもミスが発生することから、意味がないと言われることもあります。
ここからは、ダブルチェックが形骸化して意味がないと言われる理由や見落としが発生する理由を解説していきます。
脳の思い込みにより見落とし
「ミスはないだろう」と思っている人がチェックすると、ミスを見落としやすくなります。
人は「大丈夫だろう」と思い込んでチェックすると、ミスが目に入っていてもミスと認識できないことがあります。
「ミスは起こる」と意識してチェックすることが大事です。
リンゲルマン効果による手抜き
リンゲルマン効果(社会的手抜き)とは、「自分1人で作業するより、複数人で作業するときの方が無意識に手を抜いてしまう」現象のこと。
自分が見落としても誰かがミスを発見してくれるだろう、他の人が確認するだろうと思っていると、ダブルチェックが形骸化してしまいます。
実際に社会的にダブルチェックで手抜きが発生していることを示した研究もあり、その中では、「チェックを1回だけ行う場合よりも複数回行う場合に個々のヒューマンエラー検出率が低下することを示している。」と述べられています。
※公益財団法人鉄道総合技術研究所. 重森雅嘉. “ダブルチェックの社会的手抜き”. https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/library/docs/citation4.pdf, (参照2025-02-04)
業務量増加によるミス発生
ダブルチェックを行う場合、1人当たりの作業量は増えます。
仕事が忙しいときに確認作業をしても、いい加減なダブルチェックとなり意味がないでしょう。
ダブルチェックをする人は、余裕のある作業時間を取っておくことが大事です。
担当者の経験や能力不足
チェック担当者の経験や能力が不足していると、ダブルチェックが形骸化する要因に。
人事異動などで配置されたばかりの経験が浅い人がダブルチェックをしても、ミスがあるのか判別は難しいでしょう。
特にクロスチェックでは、十分な知識や経験がある人がチェックを担当してください。
慣れによる慢心
作業に慣れたり、長期間同じ仕事をしていたりするとチェックが甘くなることも。
ミスがあまり発生しない業務だと「今回もミスはないだろう」と思い、ダブルチェックが形骸化してしまいます。
慣れてきたときこそ気を引き締めるのが大事です。
対策としてチェック方法や担当を変えたりするのもアイデアです。
ダブルチェックを成功させる方法

ダブルチェックの見落とし対策としては、違う観点から確認したり、チェック方法を変えたりすることがおすすめ。
また、業務への理解が浅いとミスに気が付けずチェックの意味がないため、日頃からチームでナレッジを作成し共有するとよいでしょう。
そもそも、ダブルチェックを前提に仕事を進めると業務の質が落ちる原因になります。
自分が作業を行うときから集中して業務を進めましょう。
ダブルチェックの見落としミス対策とは

ダブルチェックやクロスチェックをしてもミスが発生することもあります。
ミスをできる限り少なくするために、検討したい対策を何点かピックアップしました。
ミスの原因を分析
最初に、なぜミスをしたのか、ミスを見落としたのかを分析するのが重要なポイント。
気を付けたいのは、単に注意不足と考えて終わらせないこと。
人間はミスをするものなので、人の認識力に関係なくミスを減らす対策や仕組みづくりを検討することが大事です。
ルールを変える
作業担当者によって、チェックする事項や手法が異なると、ダブルチェックの正確度にばらつきが生じます。
対策として、チェック方法や項目を明らかにし、マニュアル化して共有するとばらつきの発生を防げるでしょう。
見落としやミスを見つけたら原因を分析し、改善策をマニュアルにアップデートしていくのもコツです。
機械やデジタルツールを使う
人間が行う作業は、不注意や体調不良などからミスが発生してしまうもの。
機械やデジタルツールを導入すれば、そういったミスを回避できます。
例えば、バーコードスキャナーを使って商品をピッキングすれば、品番を間違えづらくなるでしょう。
RPAなどで作業を自動化するのもミスを減らす有効な対策となります。
まとめ
記事ではダブルチェックの言い換えから、クロスチェックといった多種多様な確認方法、意味がないといわれる要因などを解説しました。
複数回にわたる確認作業を行っても、人間の思い込みや慢心によってむしろミスを誘引してしまうことも。
人間はミスをしてしまうものなので、ミスや見落としを防止する仕組みづくりも大切です。
チェック方法を変えるほか、業務知識を付ける、ツールを導入するといった対策を取りましょう。



